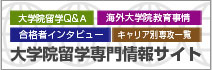Data Interpretation SetsはGREテスト特有の問題です、
特に出題形式に特徴がありますが問題自体の基礎レベルです。
Data Interpretation Setsは、
まず資料(表、グラフ)が表示され、それをもとに解く問題が3問程度出題されます。
こちら単純な数量問題ではなく、提示された表やグラフ、チャートといった資料を効果的に読むことができる知識を付ける必要があります。
通常1つのグラフや表に対して3つ程度の設問がありますので、最初に提示された表やグラフが理解でいないと大きなロスを負うことになってしまいます。提示される表やグラフはもちろん全て英語で記載されていますので、まずは英語で提示されている表やグラフといった資料を効果的に理解できるスキルを付けましょう。
出題形式
出題形式は下記2つとなり、Quantitative Comparison(数量比較問題)は出題されません。
Multiple- Choice Question(選択問題)
Numeric Entry Question(数値入力問題)
例題
具体的な例題はこちらをご確認下さい。
素早く問題を解くコツ①: 資料の読み方を間違えない
出てくるのが表にしろグラフにしろ、それが何を表すものなのか、単位は何か(例えば速度を表すとき、グラフでは時速、問題文では分速というケースがある)、複数の資料があるときはそれらがどういう関係なのかということをまず気にかける必要があります。
Discrete Questionsと違い、まずは資料がどういうものかを把握するために時間を割くことが重要です。それによりミスを減らすことができます。
素早く問題を解くコツ②: 問題文を最後まで読む
Data Interpretation Setsの特徴として、最初に資料が見えているため、具体的な数字がすでにいくつかわかっている段階で問題文を読むことが挙げられます。
そんなときにありがちなのが、問題文を最後まで読んでいない段階で「ああ、グラフのこの部分を答えさせたいんだな」と早合点し、見えている数字を答えてしまうことです。
例えば、A~Eの値を表示している棒グラフがあったとします。問題文を途中まで読んで、求めるのが「AからEまでの増加分の値」だと思い込んでいたところ、本当は「AからEまでの増加率」だったということもよくあります。そうならないように、問題文はきちんと最後まで読まなければなりません。
素早く問題を解くコツ③: それでもできる限り手早く解く
上2つと矛盾しているようですが、気をつけながらも急がなければならないのがData Interpretation Setsです。
特に前半のDiscrete Questionsで時間を使いすぎている場合など、最終的に勘で解くなんてことにならないよう、手早く解かなければなりません。
そのためには、無駄な計算はできるだけ省くことです。先に紹介した「おおよその数で計算する」というのもそうですし、目に見えるグラフの大きさなどで各項目の大小がわかるようなときは、それをもとに解いていけば時間の節約になります。
いずれにしてもData Interpretation Setsは1つの表やグラフなどに対して3つ程度の設問がありますので、まず出題された表やグラフをしっかりと理解することが非常に重要になります。提示された表やグラフを読み違えると3つの設問を自動的に間違えることになり、スコアに大きな影響を及ぼしますので注意が必要です。